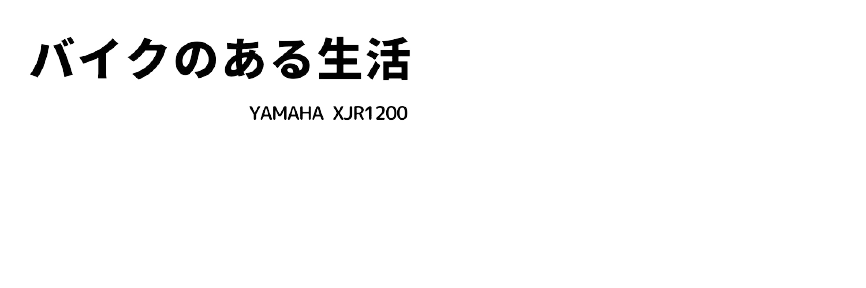最近義父が亡くなり、妻やその家族は遺品の整理や親戚への連絡等々、バタバタしてました。
死因はガンの転移等によるもので、向こうの家族はそれなりに近づく最期を覚悟はしていたようだったし、本人も生前いろいろと自分が死んだ後の決め事なんかをしていたようで、なんとなく義父の性格っぽいなと思って感じてました。
こうやって身内が亡くなると気になるのは自分が死んだ時の話。
とくにバイク乗りにとってみると、一瞬の気の緩みで命を失ってしまうかもしれないというリスクを常に背負っているわけです。
そんなとき、残した家族へのお金のことや自分の持ち物、パソコンのハードディスクに残したデータ、LINEやメールに残った特定の相手との履歴等々、死んだ後とは言え自分の尊厳を損なうようなものの処理というのは考えておいたほうがいいような気がします。
バイク乗りが事故死のリスクにそなえられる「終活」
保険で遺族にお金が残る仕組みを作っておく
下世話な話かもしれないけど、人が亡くなって困るのはお金の話。
悲しい思いをしているところにお金の心配までしないといけないのは辛いものなので、生命保険などに加入しておくことはしておきたいところ。
自分の場合コロッと死んだら収入保障の保険がおりるし、自宅のローンは無くなるので、とりあえず妻や子どもの住むところと食べる手段は残しているつもりです。
さらに公的年金には遺族年金などもあるとは言え、子供が小さいうちには将来の教育費といったことなども心配のタネなので、学資保険などを含めて慎重に判断したいですね。
ネット上にあるお金の一覧を作っておく
自分でも心配しているのは、通帳のないネット銀行なんかの残高。
最近はネット証券などを使って投資をしているひとも増えているでしょうから、どこにどういうお金があるというのは一覧として作っておいたほうが無難。

そうかといってそんなものをどう作ればいいかわからないといった人も多いはず。
現実的なのは文具屋などで売られているエンディングノートというもの。≫ コクヨ エンディングノート もしもの時に役立つノート B5 LES-E101
以前は法的な効力はなかったのですけど、こういった市販のキットを使って法務局で預かってもらうということもできるようになっているので一つの方法ではないでしょうか。
パソコンやスマホ、クラウドに残ったデータ
以前は個人のデータはパソコンの中に保存されていましたけど、最近はすべてクラウドの時代です。
エロ画像、エロ動画といった個人の趣向がバレてしまうようなものとか、特定の相手との写真など、死んでなおバレたら困るようなものも存在するといった人は、とくに注意が必要です。
特定の相手との交信履歴はどうする
今回義父の葬儀にあたって、やはり家族は義父のスマホをチェックして連絡先を確認したりしていました。
顔認証や指紋認証は優秀で、目をつぶった顔でも認証を突破できるものもあるので、遺族に言えないようなやましい関係に心当たりのある人は注意が必要。
バイク乗りに取ってドラレコは最期のダイイングメッセージ
あちこちであおり運転など、異常なドライバーによる交通トラブルが絶えません。
なかにはバイクに接触させるといった悪質なケースもあるなかで、ドラレコというのは自分が被害を受けたときに加害者の嘘を暴く最後の手段かもしれません。
それ次第では相手への刑の執行など、悔しい思いをする遺族に対して、救いの証拠になるケースも。
バイク乗りにとって事故死の可能性はゼロにはできない
今回のテーマは「バイクと死」についてという、あまり考えたくもない組み合わせでした。
でもバイク乗りに取ってみると、自分の気の緩みだけでなく、他人のあおり運転による事故や若さゆえの無謀運転による事故というのも可能性をゼロにできるものではありません。
ちなみに私が具体的に終活というものを意識し始めたのは広島の災害があってから。
人は病気や寿命だけでなく、こういった災害や交通事故などでいとも簡単に死んでしまうんです。
皆に祝福されてこの世に「生」を受けるわけなので、恩をいただいた人に感謝して旅立つというのが理想だけど、出産のときと違って死ぬときというのは予定がわからないから、いざというときのためにこういった準備をしておけるというのも良いのではないでしょうか。
そして同様に、いつ死が訪れても良いように、エンディングノートなどを使って普段言えないことなどを残しておきつつ、今生きていることを当たり前と思わず「感謝する」ということを日ごろから心がけたいところです。